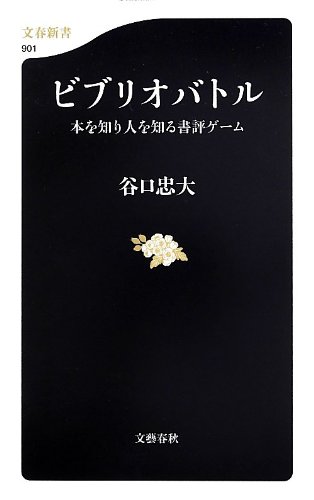文章とは何かというと、引用ができるか、内面に浮かんだことを、すでにある作品の表現や事実に結びつけられるかどうかがすべてです。引用をするためには読書が必要です。ある現象のバックグラウンドがわからなくては、いま起きていることとつなげることができない。コメントをとっても、背景とつなげて記事にすることができない。
(猪瀬直樹『言葉の力』中公新書ラクレ、2011)
おはようございます。学期末で忙しいというのに猪瀬直樹さんの『ミカドの肖像』という大部の本を読み始めてしまってこれがまたのっけからめちゃくちゃおもしろくて具体的にはフランスのロックバンド「MIKADO」との対話(1984年)で始まり「なぜそんな名前をつけたのだろう」って問いが生まれて授業でいうところの見事な導入だなぁと思いつつ頁をめくっていくと今度はアメリカのミシガン州に「MIKADO」という名称の町が存在するからレッツゴーという展開になってここでも「なぜそんな名前をつけたのだろう」って問いが生まれて単元でいうところの問いが問いを生む展開に頁をめくる手がますます止まらなくなって要するに現実逃避にマックス拍車がかかってでもこのままだと人間失格だなぁと思って強制終了すべく本を閉じかけたところ神様の悪戯なのかあるいはこれも言葉の力なのか今度はオペレッタ・ミカドという片仮名が絶妙なタイミングで「おいでおいで」してきて疲れも仕事と同じくらい溜まっていたためか抗うことができずにちょっとだけおかわりして読み進めたところ1885年にロンドンで「MIKADO」という歌劇が初演されたというこれまた好奇心を刺激するミカドが姿を現してきて万事休す。もはや仕事どころではありません。
言葉の力、恐るべし。
何せ886頁ですからね。言葉の力がなければ、読者を魅了し続けることはできません。裏表紙(文庫)には《近代天皇制に織り込まれたさまざまな記号を、世界一周取材で丹念に読み解いた、渾身の力作》とあります。では、渾身の力作を生み出した「言葉の力」とは?
ミカドにいったん別れを告げて、猪瀬直樹さんの『言葉の力 「作家の視点」で国をつくる』をパラパラと再読しました。もしも「作家の視点」でクラスをつくることができたら、どんな子どもが育つのか。そんなふうにも読める一冊です。
はじめに――国難だからこそ「言葉の力」を
第一部 「言語技術」とは何か?
1 日本人よ、世界をとらえる言葉を取り戻せ
2 絵画、サッカー、フィンランド――「言語技術」の実践例
3 「課題解決力」の身につけ方
第二部 霞ヶ関文学、永田町文学を解体せよあ
4 言葉が国の命運を決める
5 巧妙な「霞ヶ関文学」
6 政治家から言葉が消えた
第三部 未来型読書論
7 「活字離れ」防止に秘策あり
8 電子書籍は ”黒船” か?
9【都庁白熱教室実況中継】本を読んで脳に ”筋力”を
10【読書案内1】大宅壮一と三島由起夫
11【読書案内2】太宰治
終わりに――「作家の視点」で国をつくる
あとがき
目次がふるっていますよね。教育書のコーナーにあってもおかしくないタイトルが並んでいます。言語技術の実践例とか、「活字離れ」防止に秘策ありとか、小学校の教員の実践報告のタイトルとしても読めるのではないでしょうか。第二部の「言葉が国の命運を決める」は、学校でいえば「言葉がクラスの命運を決める」と読み替えることができるし、第三部の「【都庁白熱教室実況中継】本を読んで脳に ”筋力”を」なんて、まさに(理想とする)教室での取り組みそのものです。理想とするをカッコにしたのは、以下の理由から。
言語技術の基礎があってはじめて、「ハーバード白熱教室」ができる。
ハーバード白熱教室というのは、一昔前に流行ったサンデル教授のあれです。あれの説明はしませんが、小学校でいうところの「考え、議論する道徳」に近いでしょうか。つまり「考え、議論する道徳」は、言語技術の基礎がなければできないということです。正しい。ドリブルができなかったら、サッカーの試合は白熱しませんから。だからスポーツと同じように「言語技術」をトレーニングする必要があります。
例えば、絵画。
絵画を見たときに、「とても素晴らしい」とか、「いい絵だ」とか、形容詞は極力使わないほうがいい。「うれしい」「可愛そう」「悲しい」などの形容詞は、何も言っていないのと同じことなのだ。「どんな色が使われているか」「描かれた人物は何をしているのか」「何時ごろなのか」というファクトをならべていく。
例えば、サッカー。
ドイツでは、コーチが子供たちに「どうしてそういうパスをしたのか」と訊く。それを受けて、まだ12歳の子供同士が議論をする。論理的思考をぶつけ合う訓練が、あたりまえに行われている。
いっぽう日本で同じことをやると、子供たちは黙ってコーチの目を見る。コーチの用意している答えを推測して、そのとおりに答えなければいけないと思っているのだ。
例えば、フィンランド。
もともとフィンランド人は北国の寡黙な民族だった。それが欧州連合(EU)に加盟した1995年、ヨーロッパの新聞に「フィンランドはEUで何も発言しない」とバカにされた。コミュニケーションして、論理的に思考する力、すなわち読解力を身につけなければならないと、教育改革が行われた。
教育改革の結果、フィンランド人は世界でも優秀な読解力、コミュニケーション力をもつようになった。
要するに教育が大事というわけです。冒頭の引用でいうところのバックグラウンドです。言語技術や読解力を公教育の柱に据えれば、停滞というか衰退しているとしか思えない日本も、フィンランドのように変わることができる。「作家の視点」でクラスをつくれば、国は変わるというわけです。
「作家の視点」でクラスをつくる。
作家の視点ではなく単なるひとりの教員の視点ですが、現場で働いていて思うことは、授業中に話しすぎる先生が多いんじゃないかなぁ、黒板に書きすぎる先生が多いんじゃないかなぁ、ということ。先生が話せば話すほど子どもは受け身になるし、先生が書けば書くほど子どもはただ先生の後を追うだけになる。別の表現をすれば「カーナビ」みたいになっている先生が多いんじゃないかなぁ、ということです。カーナビに頼ると、道を覚えない。未知に反応しない。だから先生は、絵画の例にあるような端的で本質的なレクチャーと、『ミカドの肖像』にあるような探究する価値のある「問い」と、サッカーの例にあるような論理的思考をぶつけ合う時間を準備して、待てばいい。先生はそんなに話したり書いたりしなくていい。忖度力を鍛えるような、教師主導の「Q&A」で進んでいく板書を前提とした授業は、ほどほどにした方がいい。授業中に汗をかくのは子どもであって、先生ではない。
第三部の「未来型読書論」に出てくる三島由起夫と大宅壮一、そして太宰治については、ファクトと引用と物語が絶妙のハーモニーを奏でている、猪瀬さんの作家評伝三部作(『ペルソナ 三島由起夫伝』『マガジン青春譜 川端康成と大宅壮一』『ピカレスク 太宰治伝』)を、ぜひ。以下のブログも、ぜひ。
最後に、読書について。なぜ本をたくさん読まなければいけないか(?)という問いに、猪瀬さんは簡潔にこう答えています。
本イコール他者だからだ。
本を読むのも、人の話を聞くのも同じだというわけです。だから、学校で「他者との良質なコミュニケーション」が増えれば増えるほど、そして子どもたちが他者に興味をもてばもつほど、自然と読書量は増えるはずです。だって、本=他者なのだから。ちなみに第三部『未来型読書論』にある「『活字離れ』防止に秘策あり」の章には、ブックスタートやビブリオバトルの取り組みなどが紹介されています。今でも続いているのでしょうか。
『ミカドの肖像』という他者を手に🚃。
行ってきます。