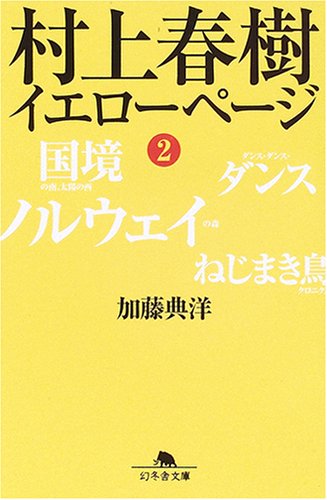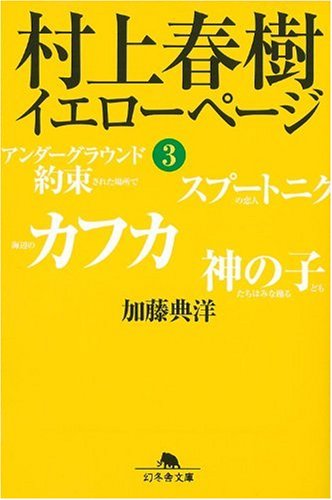「近内君、最近どう?」
ある飲み会の席で、加藤さんは気さくに声をかけてくれました。
「今、いろいろ文章を書いてみているんです。でも、文章を書くと、ああ、自分はからっぽなんだなって思い知らされるんです」
僕は思わず加藤さんにそう漏らしました。
そんな僕の取るに足らない愚痴に、加藤さんはこうおっしゃいました。
「文章を書いて、自分がからっぽだ、って思わなかったら嘘だよ」
(近内悠太『世界は贈与でできている』NewsPicks パブリッシング、2020)
こんばんは。加藤さんというのは『敗戦後論』などの著作で知られる文芸評論家の故・加藤典洋さんのことです。村上春樹さんのファンにとっては『村上春樹 イエローページ』の加藤さんといったほうがしっくりくるでしょうか。近内悠太さんの『世界は贈与でできている』の文脈に乗せれば、村上さんは贈与の差出人、加藤さんは受取人であると同時に差出人、イエローページの読者は受取人となります。
その加藤さんのことを、近内さんは《僕が文章を書くことに関して、一番初めに背中を押してくれた方》と書いています。私たちが『世界は贈与でできている』を読めるのは、その起源に加藤さんがいたからだ、ということになります。近内さんの処女作は贈与でできている。先ほどの例でいえば、加藤さんは贈与の差出人、近内さんは受取人であると同時に差出人、私たち読者は受取人になるというわけです。
受け取ったら、どうするか。
近内悠太さんの『世界は贈与でできている』を読みました。贈与の原理とウィトゲンシュタインの哲学を理解することでこの世界の成り立ちを知ろう。そして生きる意味に迫ろう。そういった本です。副題は「資本主義の『すきま』を埋める倫理学」。ちょっと難しそうに思えますが、資本主義の「すきま」だけでなく、私の「すきま」時間も全て埋め尽くしてしまうくらいにリーダーフレンドリーでめっちゃおもしろい本でした。糸井重里さんらが絶賛するだけのことはあります。
私も、絶賛。
読みやすさとおもしろさの正体はといえば、それはヴァラエティーに富んだ数々の固有名詞&エピソードの見事なまでのバトンパスにあります。テルマエ・ロマエとか小松左京とかアルベール・カミュとか、無償の愛とか郵便的誤配とか鶴の恩返しとか。親から子へ、そして孫へとつながっていく「愛」という名の贈与と同じように、これらの固有名詞&エピソードも、近内さんという、巨人の肩の上に乗った類い希なるメッセンジャーの手によって、滑らかにつながっていきます。
贈与は、受取人の想像力から始まる。
近内さんはそう主張します。贈与の原理の最大のポイントです。ちなみに「贈与」というのは《僕らが必要としているにもかかわらずお金で買うことができないものおよびその移動》のこと。贈与のカウンターパートにある「交換」(コンビニが典型)が1ターンで終わってしまうのに対して、贈与は対流します。では、なぜ差出人ではなく受取人が大事なのか。近内さんは、贈与を理解するための格好の題材として、映画『ペイ・フォワード』(ミミ・レダー監督作品)を引きます。
YがZを助けた。ZはYを知らない。ZがYにお礼を述べると、Yは「お礼はいいから、次へ渡しなさい(Pay it forward)」と告げた。私もそう言われたのだよ、と。ZはYにそう言ったというXを訪ね、さらにWを訪ね、遂には「きっかけ」であるAにたどり着いた。このAというのが、映画『ペイ・フォワード』の主人公です。Aは、Zのインタビューを受けた直後に、同級生に刺されて死にます。
なぜAは刺されたのか。
この結末は、贈与論的に考えたとき極めて正しいものだと僕は考えます。
6年生の担任が、卒業式の日に「私はたまたま最後の1年間を担任させていただいただけで、子どもたちが晴れてこの日を迎えることができたのは、これまでの担任及び職員のみなさまが~」 というような挨拶をするのは、贈与論的に考えたときに極めて正しい。学校現場の話に置き換えて解釈するとそうなります。6年担任に受取人としての想像力がなく、この挨拶を蔑ろにしてしまうと、それこそ刺されかねません。贈与論のメカニズムを考えると、Aは刺されざるを得なかった。そういうことです。
贈与は必ずプレヒストリーをもつ。
では、受取人が差出人の贈与に気づくためにはどうすればいいのか。想像力がプレヒストリーをとらえるためにはどうすればいいのか。ウィトゲンシュタインの哲学と資本主義の「すきま」がヒントになります。
私たちはウィトゲンシュタインいうところの「言語ゲーム」(常識のようなもの)に囚われている。すなわち「交換」に象徴される資本主義(市場経済)に囚われている。でも、囚われているからこそ、その「すきま」に生まれる「偏差・逸脱」としての贈与に気づく可能性に開かれている。ちょっと難しいですが、そういう理路です。
つまり、これまで述べてきた贈与は、現在の世界を覆い尽くしている市場経済と一切矛盾しません。
しかし、市場経済を否定しない代わりに、祈りと想像力が要請される。
学級崩壊という現象があります。担任であれば誰もが「教室の壊れやすさ」を知っています。それはちょうどSF作家の小松左京が「世界の壊れやすさ」を知っていたのと同じです。壊れやすい教室を、壊れやすい世界を、コロナ禍の今で言えば「壊れやすい医療」を、陰で支えている人たちがいる。そういったアンサング・ヒーローたちへの「祈りと想像力」がなければ、贈与は止まってしまい、世界は壊れてしまうかもしれない。近内さんは小松左京の『復活の日』を引きつつ、そう説明します。
贈与の受取人は、その存在自体が贈与の差出人に生命力を与える。
教室が壊れないように壊れないようにと、アルベール・カミュのシーシュポスよろしく未然に防ぎ続けている担任が、あたたかい保護者の存在にホッとするのは、おそらくはそういった理路でしょう。シーシュポスが岩を運び上げては転げ落ちて行き、再び運び上げるという終わりのない罰ゲームを「よし」とするのも、担任が教室を消毒しては子どもたちが登校し、放課後に再び消毒するという終わりなき日常を「よし」とするのも、贈与の受取人の存在を信じているからです。
想像力のある人だけが、贈与を受け取ることができる。そして贈与のサイクルの中で生きていくことができる。近内さんは《その自覚から始まる贈与の結果として、宛先から逆向きに「仕事のやりがい」や「生きる意味」が、偶然返ってくるのです》と書きます。だから勉強しよう。
受取人としての想像力を育むためのシンプルな方法。それは勉強です。近内さん曰く《具体的に言えば、歴史を学ぶことです》云々。猪瀬直樹さんのミカド三部作なんて、うってつけではないでしょうか。では、なぜ歴史を学ぶことが受取人になることにつながるのか。
答えは『世界は贈与でできている』の中に。
これで私もメッセンジャー。