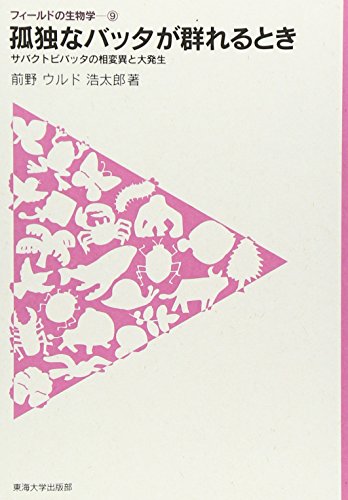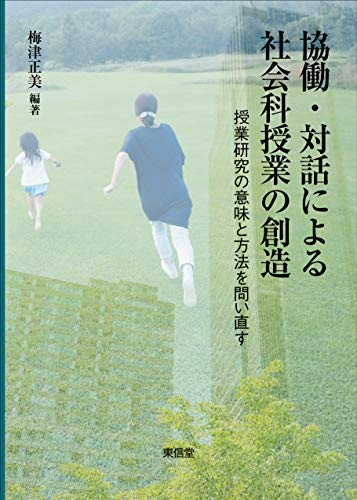学校現場での教師による研究の場合、「仮説」と「検証」の関係は、「スパイラル」にはなっていません。「仮説」から「検証」への一方向的なものになっています。
というのも、一つには、基本的に、当初立てた「仮説」が否定されることはありません。~中略~。
また、もう一つには、「検証」されたはずの「仮説」が、その後、他の学校や教師らによって活用されている様子が見られません。
(石井英真、渡辺貴裕、他『流行に踊る日本の教育』東洋館出版、2021)
こんばんは。もしも学級人数の上限が35人や40人ではなく20人になったら。もしも残業時間を正しく反映した給与が教員に支給されるようになったら。もしも授業準備&片付けにかかる時間や休憩時間が8時15分から16時45分の間に形式的にではなく現実的・実質的に確保されるようになったら。そうなったら、日本の教育はどうなるのだろう。
検証してみないとわかりませんが、教員採用試験の倍率が過去最低を記録するなんてことも、精神疾患を理由に退職した教員が過去最多を記録するなんてこともなくなるだろうし、教員も子どもも健康で文化的な毎日を送ることができるようになるだろうって、そう思います。「仮説ー検証」図式を採用するのであれば、流行に踊ることなく、そういった研究をどこかの都道府県でやってほしい。
岩瀬直樹さんが勧めていた『流行に踊る日本の教育』を読みました。京都大学大学院教育学研究科准教授の石井英真さんをはじめとする、10人の大学人(上記)によって編まれた一冊です。
読み始めた。これからの教育を考えたり、実践したりする人は、これくらいは目を通しておきましょう。基礎文献です。 pic.twitter.com/BAfDDT4W6g
— Naoki Iwase (@gorigo) January 11, 2021
大学人に執筆を依頼するに際して、編集代表の石井さん曰く《この人がこの問題をどう考えるのかを聞いてみたいという具合に、人をとても重視しました》とのこと。この問題というのが、以下の目次に並んでいる各章のタイトルです。
序 章 新しいものにとびつく前に、当たり前をやめる前に
第1章 資質・能力ベースのカリキュラム改革 ー学校ですべきこと、できることは何か?
第2章 個別化・個性化された学び ー「未来の学校」への道筋になりうるか
第3章 対話的・協同的な学び ー新しい知と文化が生まれる学校を目指して
第4章 プロジェクト型学習 ーカリキュラムにおけるプロジェクトは「メソッド」の再来
第5章 インクルーシブ教育 ー「みんなちがって、みんないい」の陰で
第6章 教師による「研究」 ー「仮説-検証」という呪縛
第7章 外国語コミュニケーション
第8章 大学入試改革 ーそれで高等教育は本当に変わるのか?
第9章 エビデンスに基づく教育 ー黒船か、それとも救世主か
第10章 社会に開かれた教育課程 ーカリキュラム・マネジメントと「地方創世」
座談会 いま一度、立ち止まり、語り合っておきたいこと
大学の工学部を卒業した後に教員となり、複数の県の小学校で研究主任を経験してきた身としては、東京学芸大学教職員大学院准教授の渡辺貴裕さんによる第6章「教師による『研究』」が印象に残りました。冒頭の引用も含め、我が意を得たりです。
渡辺さんは、学校で行われる研究に対して「面倒なもの」というイメージを抱いている教員が結構な割合で存在すると指摘し、その理由を《「研究」というものが、ある種の偏りをもってとらえられてしまっているためかもしれません》と書きます。つまり、
そのイメージは間違っている、ということ。
故スティーブ・ジョブズの言葉を借りれば「Think different.」となります。ある種の偏りというのは、いわゆる「仮説ー検証」図式を用いた研究のことで、一般には「論理実証アプローチ」と呼ばれます。
「仮説ー検証」図式が、学校現場での教師による研究において使われ続けている背景には、この図式を用いなければ「研究」にならないという強固な思い込みが存在すると考えられます。
観察実験を重視した知的感動体験のある理科の授業を展開すれば、児童は理科が好きになるだろう。そういった「〇〇すれば、〇〇になるだろう」という「仮説ー検証」図式を用いて研究を行っている小学校が、田舎にも都会にも「未だに」たくさんあります。
知的感動体験のある理科の授業を展開すれば、児童は理科が好きになるだろうって、そりゃそうだ。渡辺さん言うところの《否定されず、「検証」後に活用もされない「仮説」》の典型です。工学部での「仮説ー検証」との違いに、何だかなぁと思います。
バッタを相手にした研究と子どもを相手にした研究とをこのように並べて考えることはナンセンスに思われるかもしれません。けれども、そうであるとすれば、自然科学分野での研究で用いられてきた、「仮説ー検証」図式をはじめとするやり方を、学校現場での研究において無反省なまま使い続けることは、なおさらナンセンスではないでしょうか。
バッタというのは前野ウルド浩太郎さんの研究のこと、無反省なままというのは、学校現場で使われている「仮説ー検証」が、サイエンスのそれと違って「汎用性に欠ける」ことを指します。指導案に参考文献すら明記されませんからね。それこそナンセンスです。
Think different.
では、「仮説ー検証」図式のような「論理実証アプローチ」ではない研究の在り方にはどのようなものがあるのでしょうか。渡辺さんは、南浦涼介さんの「協働・対話という視点によって授業の何が見えるか?」という論文を参考文献として、次のように書きます。
南浦によると、「社会文化的アプローチ」の授業研究は、「一般的・普遍的な理論の構築」を目的とするのではなく、その状況がもつ一回性・固有性に注目し、「その場の中における意味」を解き明かすことを重視し、「主観的であることを厭わ」ず、「共感可能」な形で「物語的に場を描く」ことを行うものです(26頁)。
論理実証アプローチではなく、社会文化的アプローチ。前者がNGで、後者がOKという話ではなく、研究の枠組みに自覚的になることで、両者をミックスさせたり、その他の可能性を探ったりすることができますよというサジェスチョンです。ミックスというのは、
つまり、教師一人一人が「〇〇すると〇〇になるのではないか」という仮説を立てて日々の授業や研究授業のなかで検証を試みることを行い、そうした試行錯誤の軌跡を互いにもち寄って校内で交流する、というものです。
勤務校の研究スタイルは、このかたちに近いように思います。次年度もそうありたいな。何らかのエビデンスがあれば、提案が通りやすいのですが。広島大学大学院人間社会科学研究科准教授の杉田浩崇さんによる第9章には、エビデンスのことが書かれています。
「エビデンスに基づく」に踊らされないために。
第6章に続いて興味をもったのが、第9章の「エビデンスに基づく教育 ー黒船か、それとも救世主か」です。第6章では自然科学分野の研究と学校の研究が比較され、第9章では教育と医療が比較されています。教育はナラティブベース、医学はエビデンスベース。
上記のブログで書いたことと似ているなって思いました。ナラティブとエビデンス、換言すれば「不易」と「流行」というような二項対立に踊らされてはいけないということ。第6章と第9章以外の章も、例えば「一斉授業による学び」と「個別化・個性化された学び」のように、同様のかたち、すなわち二項対立を超える流れで議論が進められていきます。いずれにせよ、副題にあるように、本当に大切なことは、私たちの足元にある!
まずは足元を照らす基礎文献を。
そして、Think different!