もともと僕は建築家を志望していたし、その後も建築のことを中心に何かを伝えようとしてきた。しかし、何か違和感を感じていた。何か違うと。
それが料理をはじめるようになって少しずつわかってきた。
僕が伝えたいと思っていることは外枠の建築ではなく、その中で暮らす人々の姿、もっというと、彼らが集まり料理を一緒に食べている姿なのである。
(坂口恭平『cook』晶文社、2018)
こんにちは。昨日、ケン・ローチ監督の話題作『家族を想うとき』を観てきました。労働者階級や移民、貧困などの社会問題に焦点を当てた作品をつくり続けてきた社会派の監督が、引退を撤回してまで撮った作品です。映画は、働き方の問題と家族の問題をあぶり出しながら、こう問いかけます。
いったい何と闘えば、家族を幸せにできるの?

いったい何と闘えば、家族を幸せにできるの?
『家族を想うとき』は、パートタイムやゼロ時間契約、それから「インターネット経由で、非正規雇用者が企業から単発または短期の仕事を請け負う働き方や、それによって成り立つ経済形態」を意味する、いわゆるギグ・エコノミー(Gig Economy)に焦点を当てた作品です。
家族を守るために早朝から夜遅くまで休憩時間もトイレに行く暇もなく働き続ける両親と、パパやママを仕事に奪われおかしくなっていく子どもたち。親は子どもを想い、子どもは親を想います。映画では、誰もが家族を想っています。でも、家族のかたちは崩れていくばかり。エンドロールが流れはじめた途端、救いのないその突然の終わり方に、観客席から「えっ」という声が漏れました。おそらくはその場にいたほとんどの人たちの想いを代弁した「えっ」です。
私たちは皆、この中にいる。(By 武田砂鉄)
映画を観ながら、定額働かせ放題と揶揄される教員の労働環境に焦点を当てたとしても、同じような内容の映画が撮れるだろうなと思いました。働き方の問題も、親の働き方に振り回される子ども(家族)の問題も、そっくりそのまま日本の教員やその子どもが抱えている問題と重なるからです。いったい何と闘えば、働き方をまともなものに変え、家族を幸せにできるのでしょうか。
同僚でしょうか。
管理職でしょうか。
教育委員会でしょうか。
文部科学省でしょうか。
政治家でしょうか。
保護者を含む社会全体でしょうか。
或いは、自分自身でしょうか。
「何と」に対する答えは提示されませんが、ケン・ローチ監督は《私たちがやらねばならないことはひとつ。耐えられないことがあれば、変えること》と言います。変えることによって、おそらくは次のようなシーンを日常に取り戻すこと。

『家族を想うとき』の劇場用パンフレットのちょうど真ん中にこの写真が使われています。映画の中に出てくる、数少ない「救われる」シーンです。しかし、ただの食事のシーンが「滅多にないもの」として描かれてしまう社会って、どうなのでしょうか。映画では、この小確幸も、仕事の電話によって中断を余儀なくされてしまいます。
彼らが集まり料理を一緒に食べている姿。
このシーンを観たときに、年末に読んだ坂口恭平さんの『cook』を思い出していました。坂口さんは建築家でもあり小説家でもあり音楽家でもあり画家でもあり料理をする人でもあり、それから病んでしまった人たちにとっての最後の砦でもある「いのっちの電話」というノーベル平和賞級の取り組みもしている、よい意味での「まとまらない人」です。おそらくはよき父よき夫でもあります。そのまとまらない人である坂口さんが、外枠の建築ではなく、「彼らが集まり料理を一緒に食べている姿」を伝えたい、と書いていることと、ケン・ローチ監督が伝えたかったことが同じような気がしたのです。
色とりどりの料理と日々の思索が綴られている、写真付き料理日記『cook』。巻末に収録されているエッセイ「料理とは何か」の中で、坂口さんは料理の起源に立ち返り、次のように書きます。
人間とは料理である。
生きることは料理である。
「今の時代に、足りないものはそれだけかもよ」と料理は僕にそっと言った。
坂口さんの言う「足りないもの」と、ケン・ローチ監督が映画を通して伝えたかったことは、つながっているような気がします。近しい人たちと料理をつくり、味わい、楽しむ時間くらい、日常の中に取り戻そうよ。建築も社会も、それから映画の中でパパやママが求めているマイホームも、「彼らが集まり料理を一緒に食べている姿」を生むための外枠であり、それを蔑ろにするような外枠だったら、要らない。或いは変えていかないといけない。『家族を想うとき』と『cook』は私たちにそっとそう言っています。
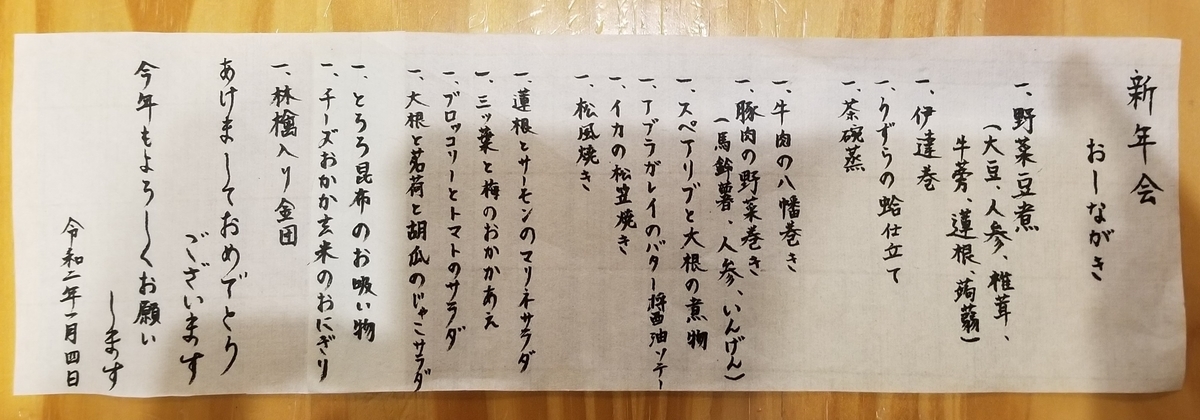
年越し蕎麦、お節料理、お雑煮、七草粥、お汁粉と、年末年始にたくさんの伝統料理があるのは、人間とは料理であり、生きることは料理であるということを忘れないようにするための先人の知恵なのかもしれません。家族を想うのであれば、まずは料理を。
闘いはそれからだ。

