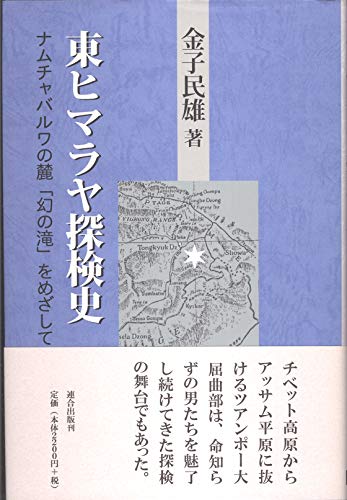岸壁を高巻き始めたのが午後一時だった。ジャングルの中で格闘しているうちに日没が近くなり、あたりは次第に暗くなり始めた。高巻きを終えるのに二、三時間と考えていたが、一向に岩壁を越えられそうになかった。山のスケールを見誤っていたのだろう。川や尾根が日本の山よりはるかに大きいのに、私は同じ感覚で登り始めていたのだ。水を持ってくるべきだった。異常にのどが渇く、だがもう少しで沢に到着するはずだ。そう言い聞かせながら私は腐った地面を登り続けた。しかし途中で大きな岩場を越えた時に、ついに日が沈んでしまった。それでものどの渇きに耐えられず、なんとしてでも沢まで行くつもりで、ヘッドランプをつけて行動を続けた。バカな判断だった。
(角幡唯介『空白の五マイル』集英社文庫、2012)
おはようございます。4月、管理職から「職員室が密にならないように、なるべく教室で仕事をするようにしてください」と指示がありました。そして11月。今度は「すぐにヘルプに行けるように、授業がないときは職員室で仕事をしてください」と指示がありました。朝令暮改をもじれば、春令秋改です。ヘルプを必要とするクラスの担任は、子どもたちの実態を見誤ったのかもしれません。春から秋までの誤った判断の積み重ねが、しんどいクラスをつくります。
バカな判断だった。
角幡唯介さんの『空白の五マイル』を読みました。副題は「チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む」。著者自身の二度にわたる探検とツアンポー峡谷の探検史が交互に描かれているノンフィクションです。
タイトルが記念碑的に美しい。
タイトルだけでなく、内容も美しいことから、多くの読者が惹かれたのでしょう。角幡さんの出世作となったこの本は、開高健ノンフィクション賞をはじめとする数々の賞を受賞しています。
世界最大の規模を誇るチベットのツアンポー峡谷に残された、人跡未踏のファイブ・マイルズ・ギャップ。
この言葉が持つ美しい響きは、大滝の伝説に変わる新たなロマンをツアンポー峡谷に与えることになった。現代の探検家たちは空白の五マイルを伝説的な未探検地と呼び、その言葉に魅せられたかのように、キングドン=ウォードの残した最後の空白部に新たな冒険を見いだしたのだ。
大滝の伝説というのは、19世紀後半にキントゥプというインド人の探検家が報告書にその存在を記述した幻の滝のことです。その後、いったんは「誤報」として探検家の主たる関心から遠ざけられていましたが、キングドン=ウォードの「空白の五マイル」という美しい言葉によって、再び脚光を浴びるようになります。漫画『ONE PIECE』(ワンピース)でいえば、ゴール・D・ロジャーの遺した「ひとつなぎの大秘宝」みたいなものでしょうか。1998年、大学4年生のときにツアンポー峡谷の存在を知った角幡さんは、その後、実際に現地に行ったことのある人を見つけ、彼らの話を聞くなどして知識と夢を蓄え、いつの間にかどっぷりはまって「こんなつもり」になります。
一年以内に滝を発見し、新聞に取り上げられ、雑誌の取材を受け、夜10時から始まるニュース番組にゲストで登場し、英国王立地理学会で基調講演し、違いが分かる男としてインスタントコーヒーのテレビコマーシャルに出演する。そんなつもりでいたのである。
その「違いが分かる男」がツアンポー峡谷の存在を知ったのは、一冊の本がきっかけです。大学4年生のときに池袋の大型書店でたまたま手に取ったという、金子民雄さんの『東ヒマラヤ探検史』。なぜ手に取ったのかといえば、「ナムチャバルワの麓『幻の滝』をめざして」というベタな副題が気になったから。当時、角幡さんは重度の探検渇望症に感染していたそうで、幻の滝という言葉が蜘蛛の糸のように思えたのでしょう。曰く《この時はまさか、それから十二年間にわたり、この本が私の人生を支配することになろうとは思ってもみなかった》云々。神田の洋書専門店でたまたま手に取ったアラスカの写真集にその後の人生を支配されたという、故・星野道夫さんのエピソードを思い出します。
「伝説の滝が本当にあると分かった時は、すごく興奮した。ツアンポーに大滝があるなんてみんな単なる幻想だと思っていたが、本当にあったし、考えていたよりも大きなものだったよ」
この台詞を言うのが、22歳だったときの角幡さんの夢だったようです。しかし残念ながら、上記の台詞は別の探検家に言われてしまいます。角幡さんがツアンポー峡谷の存在を知ってから1年と経たないうちに、米国のイアン・ベイカーらが空白の五マイルに足を踏み入れ、伝説の大滝を発見してしまうんですよね。違いの分かる男、心底がっかり。とはいえ、まだ空白の五マイルを踏破した人はいない。さすが違いの分かる男です。立ち直りが早い。ダバダ~。
私はツアンポー峡谷の探検史というパズルに残された最後の1ピースを、自分ではめ込もうと決めたのだ。
整理します。
1998年の春 角幡さんが金子民雄さんの『東ヒマラヤ探検史』に感化される
1998年の夏 角幡さんが探検部の仲間四人とツアンポー峡谷を偵察しに行く
1998年の冬 イアン・ベイカーが空白の五マイルにある幻の滝に初めて到達
2002-03年 角幡さんの「空白の五マイルを巡る探検」その1
2009-10年 角幡さんの「空白の五マイルを巡る探検」その2
ちなみにその1とその2の間に角幡さんは新聞社に就職し、5年間、記者として活躍しています。賢い。そして粘り強い。
冒頭の引用は2002ー03年の探検からとったものです。少し飛んで《転がりながら、つかんだその細い木が手のひらからずるりと抜けていくのが見えた。絶望的な光景だった。その瞬間、自分は死ぬんだと分かったのだ》と続きます。滑落です。
バカな判断だった。
滑落や雪崩といった突発的なアクシデントだと、認識が事態の急激な変化に追いつけないため、恐怖や不安を感じる時間的な余裕がない。だが今回は真綿で首を絞められるみたいに状況がじわじわと悪化したため、ついに土俵際に追いつめられたと実感せざるを得なかったのだ。
どうしたら生きのびることができるのだろうか。
これは2009-10年の探検からとったもの。2回目の探検でも誤った判断の積み重ねがあったというわけです。学校でいうと、しんどいクラスに当てはまるのは、1回目の探検の「滑落」ではなく、おそらくはこちらの「真綿で首を絞められるみたいに」という状況でしょうか。さて、土俵際に追いつめられた場合、どうしたらクラスを立て直すことができるのか。ちなみに角幡さんは、1回目も2回目も運よく危機的な状況を乗り越え、その後、心が震えるような感動を体験しています。
危機があるから、驚喜もある。
危機があるから、驚喜もある。この時期にしんどくなっているクラスを、何とか立て直すことができれば、驚喜もあるだろうし、その後につながる体験知を得ることもできるだろうって思うのですが、渦中にいる間はなかなかそうは思えないのが実際のところです。わたしも5年目のときにちょっとしんどかったなぁ。でも、いま振り返ると、そのときの経験がとても役立っていることがわかります。探検と違って、命を落とすわけでもないし。あっ、でも病にはなるなぁ。探検にも学級経営にも、しんどさはつきものです。
グッドラック。