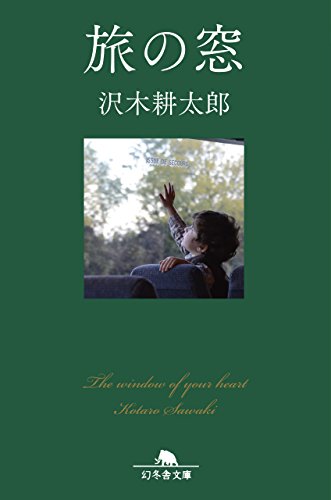でも親以外の世界に触れると、そのバランスが変わるの。成長する中で面白いと思うのは、私くらいの歳の子が家族以外の人間と会い始めると、世界が広がった感覚になり、より多くの人を受け入れるのよ。でもミラの親にとってそれはなかなか簡単に処理できることではないの。娘は人生を最後まで全うできないだろうから、その愛を貫く時間がとても限られているのを知っている。美しくも、複雑な関係性ね。
(劇場版パンフレット『BABYTEETH』クロックワークス、2021)
こんばんは。ようやくあゆみを手放しました。あゆみというのは通知表のことです。手放したと言っても、下書きを管理職に提出しただけですが。今回もまた、締め切りギリギリ。
仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する。
パーキンソンの第1法則です。先人がそう警告しているのに、映画館に行ってる場合ではありませんでした。16歳の長女に「仕事、終わるわけないよね。ひとりで映画なんて観に行ってるんだから。自業自得だよ。ねっ、ママ」なんて言わせている場合でもありませんでした。私とあゆみとの、
美しくも、複雑な関係性。

あゆみからの逃走。
長女と同じ16歳の女子高生が主人公ということで、表向きは「娘のトリセツ」を手に入れるため、内実は「現実逃避」のため、10日ほど前に映画『BABYTEETH』を観に行きました。第76回ヴェエネチア国際映画祭をはじめ、世界各国の映画祭を席巻したという、シャノン・マーフィ監督(♀)の長編デビュー作です。

Wikipediaの力を大胆に借りて、そっくりそのままストーリーを紹介すると《ミラ・フィンレイは末期の病を患っていた。そんなある日、ミラはドラッグの売人、モーゼスと知り合いになった。ミラにとって、自分を病人扱いせず、1人の人間として接してくれるモーゼスはそれだけで有り難い存在だった。当初、ミラの両親(ヘンリーとアンナ)は娘がアウトローと親しくなることを苦々しく思っていたが、娘の幸せそうな姿を見て徐々に態度を軟化させていった。そして、ミラたちに受け入れられたことで、モーゼスの荒んだ心も癒やされていき、更生への道を歩み始めるのだった》となります。
国語の授業でよくやるように、この物語を一文で表せば「手放すことの大切さを教えてくれる映画」となるでしょうか。今、生きているということ。それは、
手放すということ。
とはいえ、我が子ですからね、あゆみのようにはいきません。しかも我が子が末期の病を患っていたとしたら、なおさらです。負い目を感じますからね、親は。健康に生んであげられなかったという負い目の分だけかかわりが濃くなり、かかわりが濃くなればなるほど手放すことが難しくなります。仕事の量と同じように、我が子への愛も「完治」のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張するというわけです。
美しくも、複雑な関係性。
ミラの家族がそういった関係性を築かざるを得なかったのは、この「完治」に当たるのがミラの「死期」であり、最愛のミラがこの「死期」を迎える直前に《家族以外の人間》と出会ってしまったからです。親にとっては、特に《ミラが自分を通して幸せを感じてる時しか喜びを得られない》母親アンナにとっては、家族以外の人間、しかもアウトローの典型のような男モーゼスに夢中になっているミラを受け入れるのは、
しんどい。
小学校のクラスづくりでいうと、もと教員の岩瀬直樹さんいうところの「ぼくらの持っているコントロール欲求はなかなかやっかいだ」と似ています。
手放すのは、しんどい。
母親のアンナからはコントロール欲求が感じられる一方で、父親のヘンリーからは、ミラに対するそれが感じられません。そのことは、ヘンリーがアンナよりも先にモーゼスを受け入れ、はしゃいでいるミラにしばしばカメラを向けることからもわかります。我が子が生きていた証を遺そうとするパパ。医師という職業柄、愛情が諦観とセットになっているのでしょう。エピローグの場面にもカメラが登場していて、切なさが伝わってきます。
沢木耕太郎さんの『旅の窓』に、次のような一節があります。
大人が子供の写真を撮っているという風景はよく眼にする。しかし、子供が大人の写真を撮っているというのはあまり見かけない。子供には「いま」が大事であって、未来に向けて「記念」の写真を残しておこうなどと思わないからだ。たぶん、記念写真を撮りたがるのは、残り少ない「いま」をいとおしいと思う大人の習性であるのだろう。
病を患っていたとしても、否、病を患っているからこそ、ミラには「いま」が大事であって、未来に向けて「記念」の写真を残しておこうなどとは思わない。乳歯と永久歯は、決定的に違う。
今、生きているということ。
それは、手放すということ。
おやすみなさい。